対談 保育は人をつくり、未来を紡ぐ
対談メンバー紹介



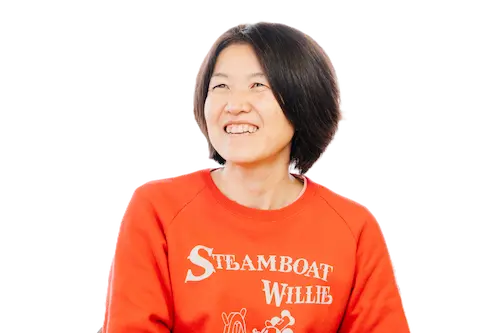
第1部:時代は変化しても、変わらないみぎわの保育の根幹
藤村先生はみぎわ保育園の開園当初から保母(現在は保育士)として勤務されてきました。私も80年代前半の乳児のころ、みぎわ保育園で藤村先生に保育をしていただいたことがあって、人生のスタートをみぎわから始めています。
当時は私の祖母が園長で、90年代半ばから父がそのあとを継ぎました。そして2018年に私が父より事業を承継し、みぎわの保育をいまの時代の保育ニーズに合った、より質の高いものにしようと努力をしているところです。この対談では、藤村先生をはじめ、みぎわとゆかりの深い職員の皆さんと、「時代は変化しても、変わらないみぎわの保育の根幹」があること、そしてそれはどのようなものなのかを掘り下げていければと思っています。まずは、みぎわの創成期がどのようなものだったのか、藤村先生からお話しいただけますでしょうか。
みぎわ保育園は、初代理事長の小野一郎牧師と、塩谷いく子・初代園長の方針のもと、キリスト教を軸とした保育を行っていました。職員はキリスト教精神を学ぶため教会に通ったり、聖書研究を職員間で行ったりしており、日々の保育のなかでも礼拝や祈りを通じて、相手を思いやる気持ち、すべてのことに感謝する気持ちを園児たちに伝え、それがその子どもたちのこれからの長い人生に活かされることを願って保育を行っていました。月に1回は小野牧師が、職員に対して聖書のエピソードを題材に講話をしていたものです。
いまのみぎわは、当時ほどキリスト教保育という側面を強調してはいませんが、それでも当時のように、キリスト教精神のあらわれである「隣人愛」と「感謝」を子どもたちに伝えたいという思いは変わっていません。

その思いは、いまのみぎわの幼児組でとくに受け継がれていますね。形式上の礼拝になることなく、毎日の園生活のなかで相手への思いやりや感謝の気持ちを子どもたちが自然と抱き、そしてその思いを表現できるようになるように工夫しています。
祈りといっても難しく捉える必要はありません。たとえば、クラスの誰かが病気になってお休みしたとき。その子はいま発熱などで辛い思いをしているであろうこと、早く元気になってまたみんなといっしょに遊べるようにと、保育士と子どもたちはその回復を祈ります。お友だちの誕生日には、その子が何年前かにこの世に生を受け、幸せになってほしいという保護者さんの願いを注がれて、いままで元気に育ってきたことにみんなで思いを馳せます。そして、その子とこれからもたのしく遊びながら過ごしていくことができるようにと、クラスのみんなでお祈りします。
祈りは特別な儀式ではなく、日常の保育に織り込まれていて、そうした環境で生活していくなか、自然と思いやりに満ちた子どもに育っていくものと信じています。

みぎわがもつ遊びへのこだわり
私はみぎわ保育園の開園時に2歳児で入園し、年長クラス(1981年度)では藤村先生が担任でした。当時の卒園アルバムに、自分の将来の夢として「ほいくえんのせんせいになりたい」と書いているとおり、これまで私の夢はいちどもブレたことはありません。京都文教短期大学を卒業後、新卒でみぎわ保育園に入ったのも、園児のとき藤村先生に強い憧れを抱いたからです。
私は、藤村先生から受けた保育を、自分も園児たちにしたいと思って保育士になりました。園児のころを思い返すと、藤村先生に「一人の人間」として向き合ってもらった記憶がよみがえってきます。自分にいつも向き合ってもらえた、自分が興味をもったことや集中してやりたいことがあるとき、その思いを受け止めてもらえて、心から満足するまで遊んでもらえた。今から振り返ると、私たち園児が遊びに夢中になれるように、保育計画や環境設定が考え抜かれ、かつ現場での臨機応変な対応があったのだとわかります。そしてそのおかげで、園児だった私は毎日「今日はこれでめっちゃ遊んだ!あー、楽しかった!」という満足感をもって家に帰っていました。
だからこそ、子どもたちが気のすむまで「遊びこむ」こと、そのための創意工夫を絶えず凝らすことが大切だと信じています。「この遊びはここまでで終わり、次はこれをしましょう」と、保育士が子どもたちの時間を大人の都合で区切ることはみぎわではしません。子どもたちは何を考え、何をしたいのか、どう感じているのか。そういった思いを受け止めて、遊びを発展させるようなかかわりを常に心がける。そして保育士も子どもたちといっしょに、めいっぱい遊びこむ。今も昔も、この姿勢がみぎわの保育の根っこにあります。こうした保育園時代の経験が、子どもが自分で考える力、自分が何をしたいのかを選んで決める力を育むのです。
あなたはあなたでいい
私は50年近く保育現場に身を置き、多くの子どもたちと向き合ってきました。そのなかでずっと大切にしてきたのは、「あなたはあなたでいい」と、ありのままの子どもをまずは大人が受け入れることです。いたずら好きなあなた、走るのが早いあなた、すこし怖がりで新しいことに挑戦するのに慎重なあなた...。みんな、そのままのあなたでいい。いろんな個性をもつ子どもがいて、ひとりひとりがその子だけにしかない輝きをもっています。
保育の仕事を始めたころは、受け持ったクラスのみんなを愛したい、愛さなくてはいけない、と気負っていたところがあったかもしれません。それでも、保育士と園児であってもやはり人と人ですから、保育現場のなかで気の合う子どもと、なかなか関係を築けない子どもとがいます。そんなときは、うまく関係を築けない子どもこそ、その「ありのまま」をまずは大人側が受け入れることです。
クラス全体をうまくまとめるという、集団に対するまなざしが「横糸」だとしましょう。これに加えて、その子のありのままを受け入れるという、個人を大切にするまなざしを持つこと。すると、その子だけがもつ優しさ、強さ、発想の豊かさ、もちろんときには弱さなどもおのずと見えてきて、子ども一人ひとりへのまなざしが「縦糸」として紡がれていきます。そうなると、子どもの側も自分を受け止めてもらえた安心感から、保育士と子どもとの関係は少しずつ築かれていくものです。

第2部:保育士を目指す人へのメッセージ
ここからは、保育士をめざす人向けのメッセージになると思います。子どもたちの意思を尊重し、遊びを展開していくなかで、子どもどうしのトラブルは避けられません。ときには、自分の思いが通らないことに不満を覚えて、問題行動をとる子もいます。そんなとき、保育士に求められることは何でしょうか。それは、「子どもの気持ちを引き出すようなかかわりができるかどうか」です。すぐに叱ってしまうと、子どもたちは自分の思いのやり場を失って、問題行動をエスカレートさせることが多いんですよ。問題行動があったときでも、「どうしたん?何が嫌やったん?」とまずは子どもの気持ちを聴く姿勢を示す。そして実際、その子に尋ねてみると、「〇〇君にぼくが遊びたいおもちゃを貸してって言ったけど、あかんって言われた」というように、自分の思いやそのときの感情を言葉として表すことができるものです。自分の気持ちを聞いてもらえた、これだけでもずいぶんと子どもは落ち着きを取り戻します。子どもの気持ちを言葉に置き換えていくようなかかわりを行う。これが大人、とくに保育士の大きな役目といえるでしょう。
子どもたちが私を「先生」にしてくれた
私は2007年に保育士としてみぎわ保育園に就職しました。私は同期とくらべてあまり自分のやりたいことを主張できるタイプではなくて、成長は遅かったのではないかと思います。それでも、保育にかける想いは人一倍強く、日々自分の保育を振り返ったり、先輩のアドバイスを積極的に吸収して実践しようとしたりして、努力を重ねてきました。
保育士として私が大切にしてきたのは、まずは先生というよりも、友だちとして子どもたちと関係を築くことです。はじめから自分は「先生」なんだと意気込まないほうがいい。新しいクラスを受け持つとき、まずは自分が友だちとして子どもに認められることをめざします。子どもたちと向き合って、毎日の活動のなかでともに遊び込んでいるうち、「この人は信頼できる、自分を受け止めてくれる、守ってくれる」ということを子どもは肌で感じてくれます。子どもに受け入れられてはじめて、保育士は「先生」になるのです。

一年間向き合った子どもたちも、年度末には次のクラスに進級していきます。そのとき、次のクラスも先生といっしょがいいと子どもが言ってくれたときや、来年も先生にうちの子をみてもらいたいと保護者さんにおっしゃっていただいたとき、この仕事をしていて本当によかったと感じます。
私が保育士になって2年目。0歳児のクラスを担当したときのことです。私の姿を見るだけで泣いてしまう子どもがいて、その子との関係づくりにずいぶん苦労しました。その子の思いを受け止め、日々の成長を見守り、辛抱強く関係構築の努力を重ねました。やがてその子は私のことを受け入れてくれるようになり、その後、年度が変わって担任は離れましたが、その子が5歳児のとき(保育士7年目)にまた担任を受け持つことになったのです。
もちろん同じ園で働いていましたから、クラスは離れてもずっとその子の育ちを見てきてはいたのですが、年長という卒園を控えた年次で最後の担任を受け持つ機会に恵まれて、その子の成長にまた主な責任をもち、毎日接する日々がはじまりました。乳児のころの子どもとの信頼関係はもちろん重要なのですが、幼児になった子どもたちから受ける信頼感や、保育士と子どもたちとの関係性は、乳児よりもっと双方向的かつ濃密で、そこに大きなやりがいを感じたものです。
年長は保育園生活の集大成となる年です。保育のなかその子が見せてくれる成長したすがた、行事で堂々と発表しているたくましい様子、そして卒園式のときに立派に卒園証書を受け取りに向かうたのもしい背中を見ると、保育のさまざまな苦労も吹き飛びます。0歳児からその子を見ていた担任として、涙が止まらなくなるほどのうれしさと、その子がこれから小学生になってみぎわから羽ばたいていくことへの一抹の寂しさとがないまぜになった、まさに万感の想いを感じました。保育の仕事のやりがい、すばらしさを知った瞬間でした。

いま若林先生のお話しをお聞きしていて、「0歳児の子を卒園まで見届けられた」、「その子の担任として全力を尽くせた」という経験があったからこそのエピソードだと思いました。保育士は長く続ければ続けるほどやりがいを感じることのできる仕事です。子どもたちのありのままを受け止め、その子のいまの姿に寄り添って遊びこむ。そのなかで子どもたちの信頼を勝ち得て、「先生」になっていく。そして、いつか来る卒園の日に、子どもたちのこれまでの成長と頑張りを心から祝福し、これからの人生に幸多かれと願う。これは何物にも代えがたいよころびですし、こんな感動とよろこびを毎年感じることのできる仕事はそう多くはないのではないでしょうか。
みぎわ保育園のように40年以上続いていると、卒園児の子どもを2代、3代にわたってお預かりすることもあって、かつての園児に保護者さんとして再会することも頻繁にあります。塩谷顧問もみぎわの卒園生で、私が保育したこともありますが、二人のお子さんをみぎわに通わせました。塩谷いく子初代園長から数えると、みぎわとの関係はもう4世代にわたりますね。また、私の教え子の関谷さんが保育士としてみぎわに戻ってきて、いまでは園長になっているというのも、とても感慨深いことです。まさに「保育は人をつくり、そして未来を紡ぐ」ものだと、改めて感じます。
保育士と子どもとともにゆっくり成長すればいい
子どもへのまなざしとして、「あなたはあなたでいい」と言いましたが、新任の保育士にも同じことを伝えたいと思っています。はじめから子どもとの関係づくりをうまくできて、保育技術もちゃんと持っていて、同僚とうまくチームワークを発揮できる、というような人はいません。それは保育現場で働くなかで、徐々に培われていくものなのです。だからこそ、若い保育士の方々には「あなたはあなたでいい。あせらなくていい。自分のペースで成長すればいい。自分の強みをゆっくり伸ばせばいい」というメッセージを伝えたいと思います。
たしかに、子どもの集団にすぐに入り込んで、いきなり遊びを展開するのは難しいものですよね。新任の保育士はまず、子どもに一対一で向き合い、じっくり遊びこむことから始めてみるといいと思います。そして子どもが困っているときに自分からスッと歩み寄り、寄り添ってみることです。それがすべての出発点になります。
保育士として現場に入ってくる若い人は、みんな心の中に「熱量」をもっていると感じています。熱量は、熱意、やる気と言い換えてもいいかもしれません。保育士を志す人は、幼いころからの夢を胸に抱いて、保育現場で子どもと向き合い、その成長を支えたい、そうしたまっすぐな思いを持っている方が多いと感じます。では、その熱量を、どう保育現場で発揮してもらうか。
私は、「やらされ感」が強いと、その熱量は発揮されないと思います。経験が浅くても、保育技術が未熟であっても、自分がどんな保育をしたいのかをどんどん提案し、そして実現できる職場環境こそが大切だと考えています。子どもに本気で向き合い、遊びこみ、保育士自身も楽しめるような保育内容であれば、多少の粗があっても、若手の裁量にまかせていくべきでしょう。若い人の感性はとても瑞々しく、中堅、ベテランにとっても刺激になるのですから。
その一方で、中堅、ベテランは若手に学びつつ、その豊富な経験を活かして若手の手本となるような保育手法や技術を伝えていかなければなりませんね。若手だからまだやりたい保育ができない、ベテランなら自由にできる、というのではなく、お互いを尊重し、意見交換を活発に行い、保育技術をお互い切磋琢磨して磨き合っていく保育集団でありたいと私たちは願っています。



















